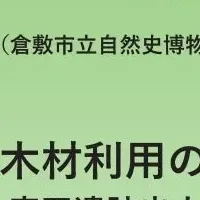
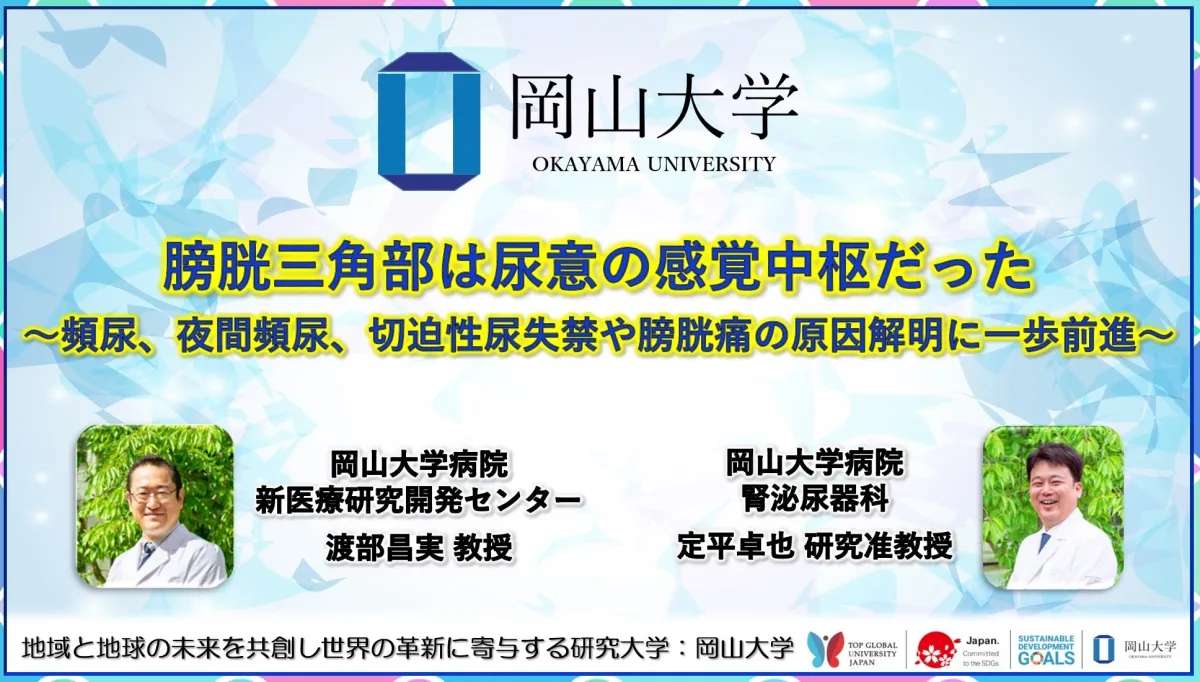
岡山大学の新発見:膀胱三角部が尿意の感覚中枢であることが判明
膀胱三角部が尿意の感覚中枢であることを解明
国立大学法人岡山大学の研究グループが、膀胱の内部に位置する膀胱三角部が尿意を感じる感覚中枢であることを発表しました。この研究は、医学界における重要な進展として注目されています。
研究の背景
膀胱三角部は、通常、排尿機能に関連する構造として知られています。しかし、最近の研究においては、単なる構造物だけでなく、感覚情報の集約拠点としても機能していることが示されてきました。特に、頻尿や膀胱痛といった症状に関与する分子群が、この膀胱三角部に集中していることが報告されています。これにより、膀胱三角部の理解が深まることで、新たな治療法の開発に貢献できる可能性が見えてきました。
研究内容
研究グループは、膀胱三角部の神経構造や分子発現の特性を文献的に考察し、多くの感覚受容体がこの領域に高密度で存在することを確認しました。具体的には、ATPや神経ペプチドが尿意や痛みの感知を中枢に伝達する役割を果たしていることが明らかになりました。また、機械刺激を受け取るPIEZO2、プリン受容体のP2X3、そしてカプサイシン受容体のTRPV1が、この部位で高い発現を示していることも分かりました。
この研究は2025年10月19日、米国の医学雑誌「Cureus」にて発表され、特に膀胱過活動症や間質性膀胱炎における異常な尿意や膀胱痛の原因解明に寄与するものとされています。
臨床応用の期待
研究者たちは今後、この知見を基に新しい治療法の開発を進めるとしています。膀胱三角部に存在する受容体をターゲットとすることで、ボツリヌストキシンなどの薬剤を用いて過剰に反応する神経を抑制できる可能性があります。このようなアプローチが、頻尿や膀胱痛といった患者の日常生活を改善する道を開くことが期待されています。
研究者からのコメント
研究グループには、渡部昌実教授と定平卓也研究准教授が含まれています。渡部教授は「患者が感じる強い尿意や痛みの背景を理解することで、新たな治療戦略を構築できると信じています。」とコメントし、一方、定平准教授は「膀胱は単なる尿を貯める器官ではなく、非常に繊細な感覚器官であることが分かった。今後、尿意そのものをコントロールする治療法の確立を目指しています。」と語りました。
まとめ
膀胱三角部の機能に関する今回の研究は、頻尿や膀胱痛に悩む多くの患者にとって希望をもたらすものとなるでしょう。岡山大学の研究者たちによる新たな治療法開発に対する期待は、今後も高まるばかりです。新技術が実用化される日を心待ちにしたいものです。
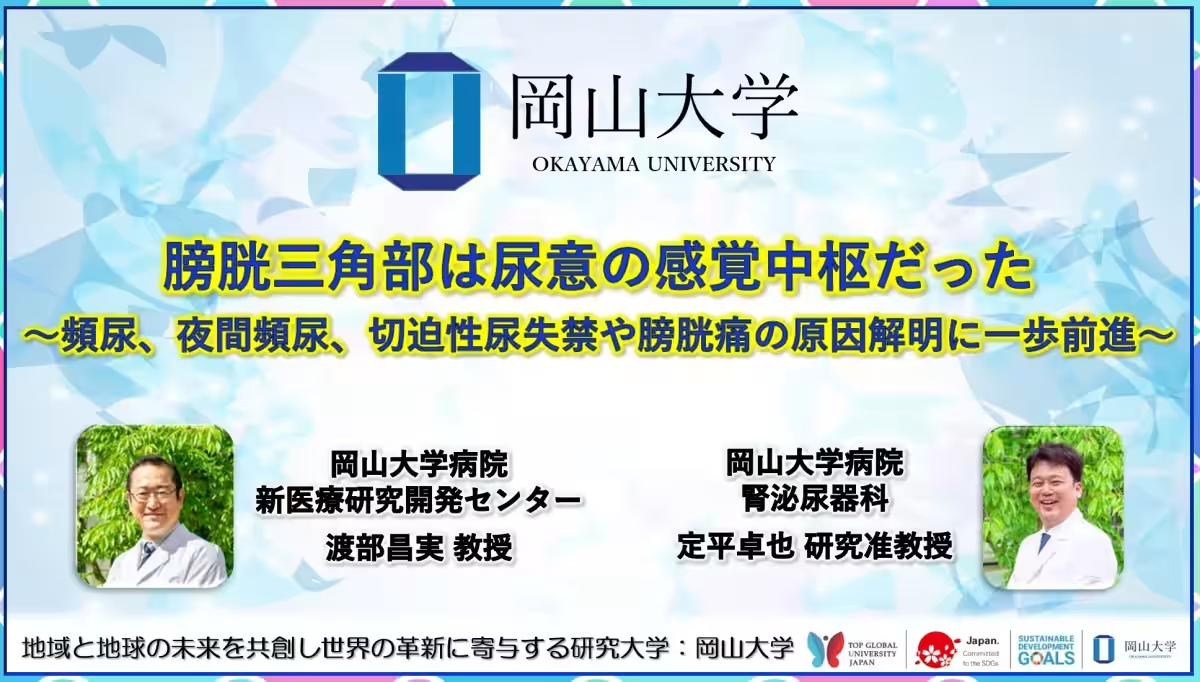








トピックス(その他)
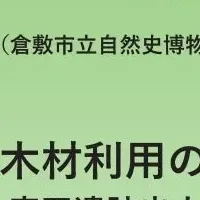
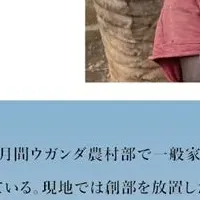
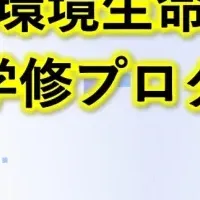




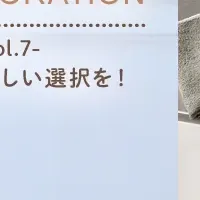


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。