
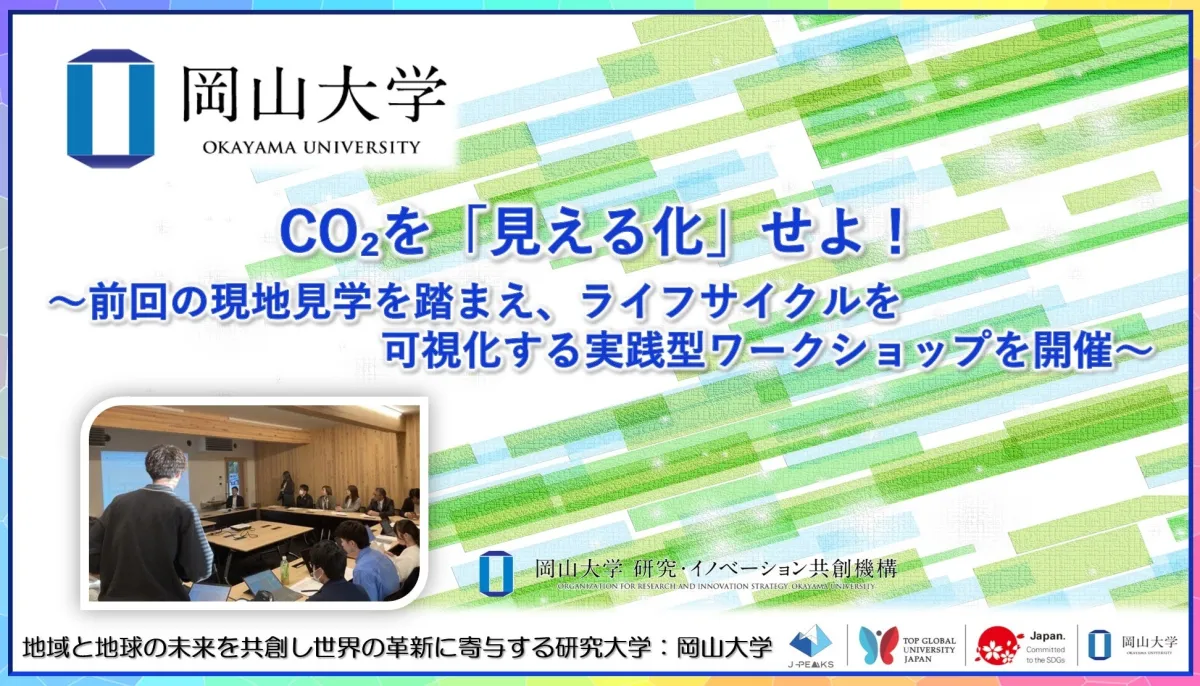
岡山大学が学生と地域企業と共催するCO₂排出ゼロへの挑戦
岡山大学が募集するCO₂可視化チャレンジ
岡山大学が2025年11月10日、商工会連合会と手を組み、学生と地域企業が共にCO₂排出量の可視化を目指すワークショップを愛媛にある津島キャンパスで盛大に開催しました。この取り組みは、令和5年度からの連携協定に基づき、地域企業のカーボンニュートラルを学生たちがサポートする実践的な教育研究の一環です。
前回の見学では、学生たちがシバムラグループのブルーベリー農園や加工所を訪れ、農産品の生産や流通のプロセスを体験し、地域のインフラの重要性を実感しました。その経験を踏まえた今回のワークショップでは、シバムラグループの芝村啓三代表などが参加し、学生たちは知識を実践するチャンスを得ました。
参加者たちは、農業から製品の流通、消費、そして廃棄に至るまで、ブルーベリージュースとポン菓子を題材にカーボンフットプリント(CFP)の算定に取り組みました。冒頭では、天王寺谷准教授がCO₂の可視化が企業経営にもたらす意義について講義を行い、実際の製品を通じてどのようにデータを収集するかの基礎を学びました。
学生たちは、製品が抱える環境への影響を直に感じながら、具体的な質問をシバムラグループの社員たちに投げかけました。一方で、農業における農薬の使用や輸送手段についての議論も交わされ、全体のライフサイクルフローを検討しました。このように、実践を通して得た知識を現場の人々と共有することで、より正確な算定を行う重要性を学びました。
ワークショップの最後には、各グループが整理したデータ収集方針について共有し、中電環境テクノス株式会社の高田氏からJクレジット制度の説明もありました。このような新しい見解が、今後のカーボンオフセットやクレジット創出に繋がる可能性を示唆しました。
参加した学生たちは、過去の見学での理解が浅かったことを痛感し、現場での対話を通して理解を深めていったことに感謝の意を示しました。今後、この研修を経て、必要なデータを収集し、年内にブルーベリージュースとポン菓子のCFP算定を完了させる方針です。そして、2026年1月19日には、その成果を発表する報告会が計画されています。
岡山大学のこの取り組みは「地域ぐるみでの脱炭素経営支援モデル事業」の一環として実施されており、持続的な未来に向けた地域価値の創造を目指しています。このような活動を通じて、岡山大学は引き続き地域社会と連携し、環境問題に挑戦し続ける所存です。
以上、地域に根付いた学びを通じて、より持続可能な未来を育む岡山大学の取り組みを、今後とも注視していきたいと思います。
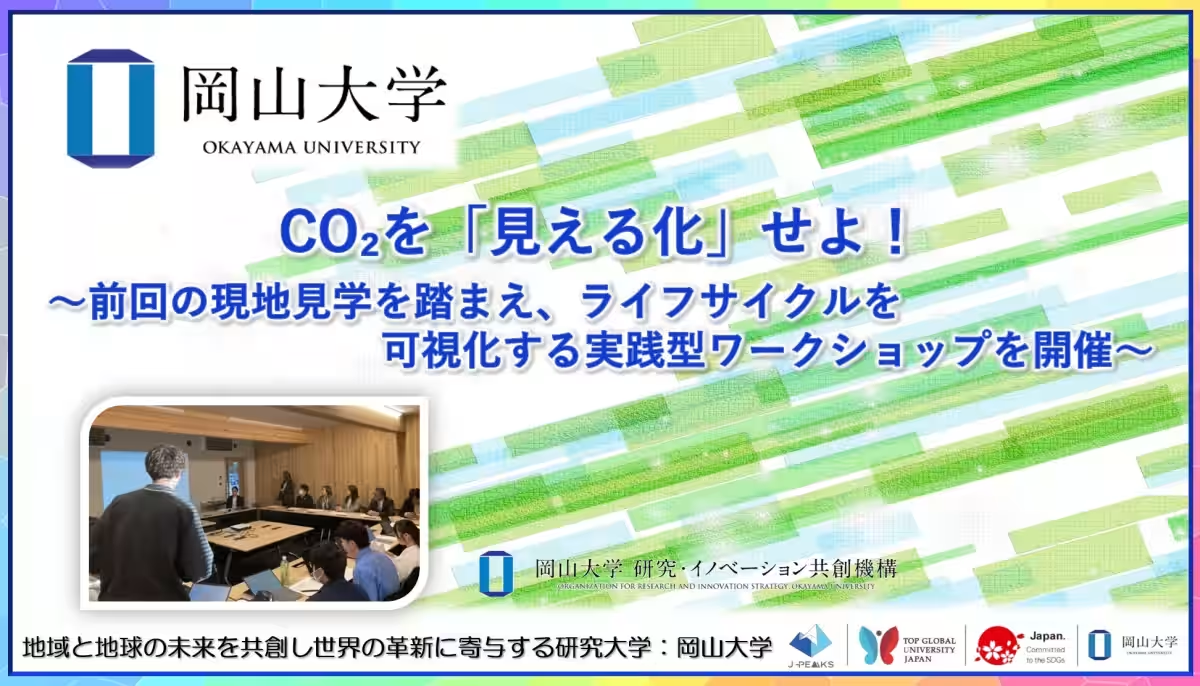









関連リンク
サードペディア百科事典: 岡山大学 カーボンフットプリント CO₂削減
トピックス(イベント)










【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。