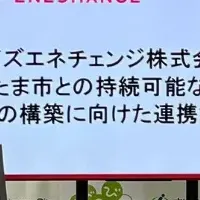
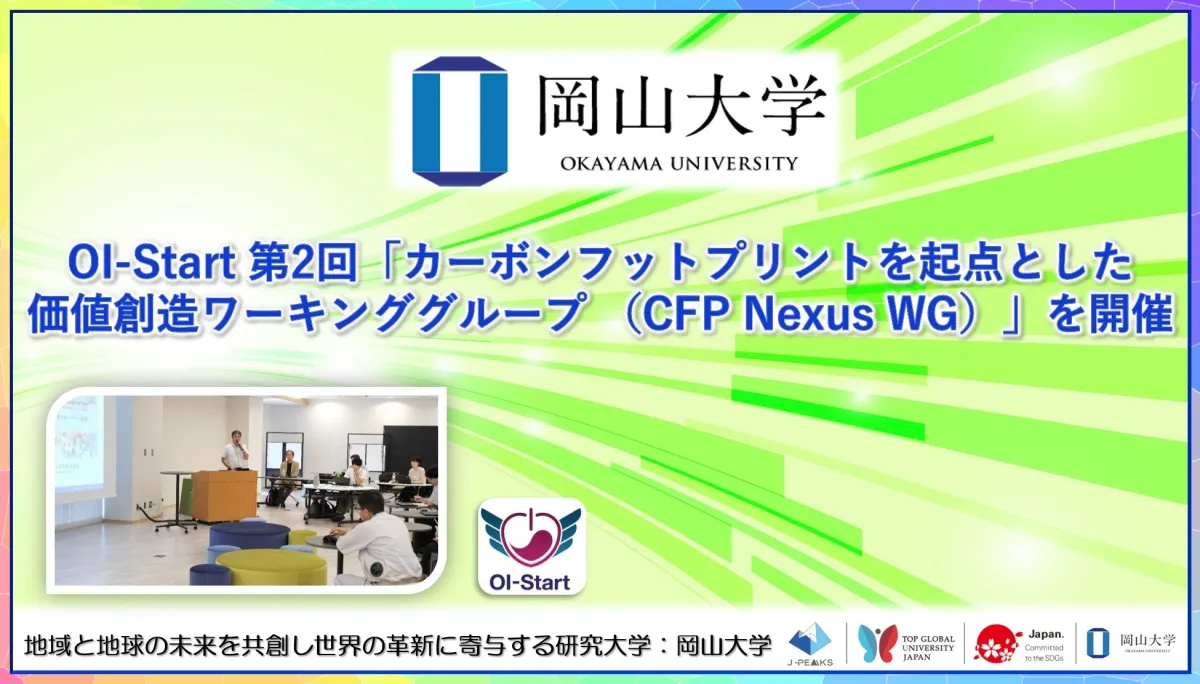
岡山大学が開催したカーボンフットプリントに基づく価値創造ワーキンググループの概要
岡山大学が推進するカーボンフットプリントの価値創造
2025年7月31日、岡山大学の津島キャンパスにて『カーボンフットプリントを起点とした価値創造ワーキンググループ(CFP Nexus WG)』第2回の会合が行われました。本会議は、国立大学法人岡山大学が事務局を務める『おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム(OI-Start)』の一環で、地域の産業界と学術界の連携を強化し、持続可能性を追求するための重要なステップです。
このワーキンググループでは、カーボンフットプリント(CFP)を活用し、地域企業の競争力向上やグリーントランスフォーメーション(GX)の実現を目指しています。そのため、産学官金の各セクターから約50名の参加者が集まり、熱心な議論が交わされました。
企業の取り組みと成功事例
会議は、まず株式会社メタルワン菱和の流田龍扶社長のプレゼンテーションからスタートしました。彼は、鉄鋼流通業におけるカーボンニュートラルの達成に向けた取り組みを紹介しました。同社は電力使用の可視化システムを導入し、省エネ運転を実現した結果、年間で約4万kWhの電力削減に成功しました。この成果は、同社が目指す「100年企業」としての理念を支えるものであり、地域企業との連携を大切にしている点が強調されました。
サーキュラーエコノミーと脱炭素支援
次に、一般社団法人サステナブル経営推進機構(SuMPO)の仲井俊文氏が登壇し、サーキュラーエコノミーと脱炭素支援の新たな提案を行いました。仲井氏は、顧客ごとの特性に基づく非効率な在庫や設備を人々が共有し、汎用化することで環境負荷を軽減できると強調しました。このアプローチは CFPP 指標を用いて排出量を計測し、取引先への環境価値提案にもつながるといいます。
中小企業向けのデータベース
最後に、同機構の今後舞氏が、中小企業にも利用可能なCFP・LCA用の排出原単位データベース『CORD』の存在を紹介しました。CORDは、専門知識がなくても扱えるよう設計されており、LCAやスコープ3の方針策定にも活用できるツールです。参加者からは、その実用性に対する高い関心が寄せられました。
今後の展望
今回のワーキンググループでは、単なるCO2算定を超えて、CFPを起点とした事業変革や新たな価値創造の方向性が見えてきました。岡山大学は、今後も地域企業や支援機関と連携し、実践的な脱炭素化とイノベーションの推進に取り組んでいく計画です。
地域の持続可能な発展を支えるためには、企業、大学、行政が協力し合うことが不可欠です。この取り組みにより、岡山地域の発展が期待されます。岡山大学の活動を今後ともご注目ください。
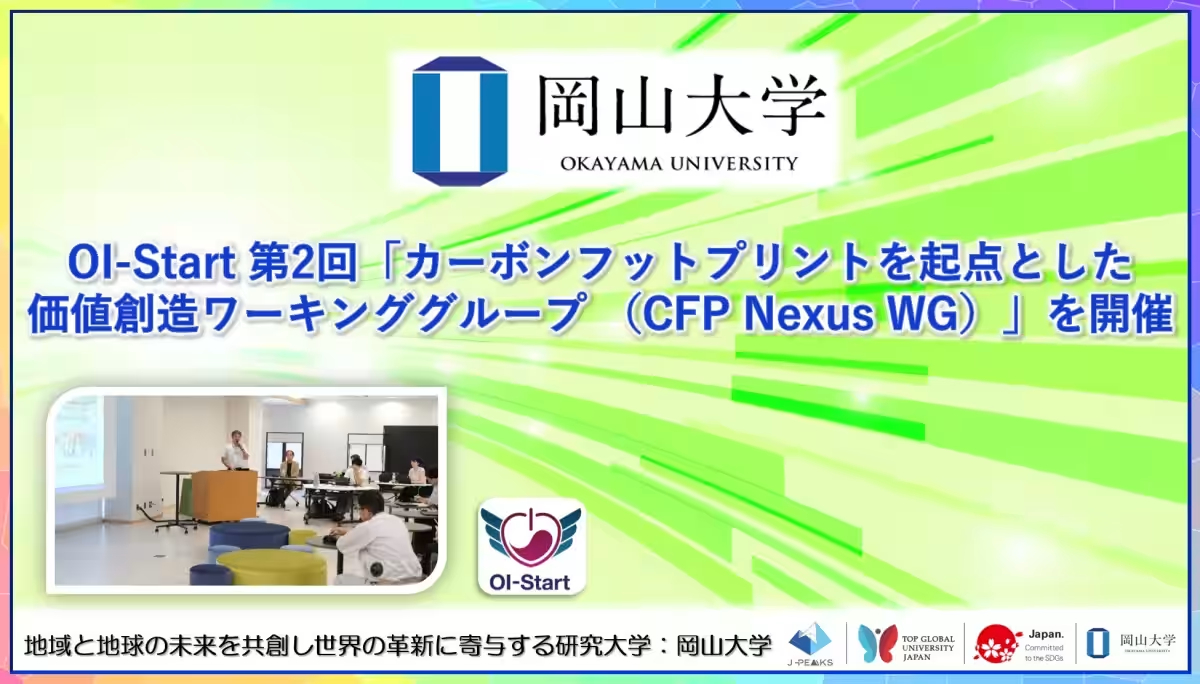










関連リンク
サードペディア百科事典: 岡山大学 OI-Start カーボンフットプリント
トピックス(その他)
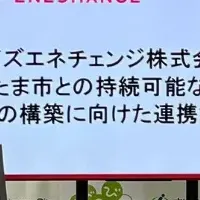
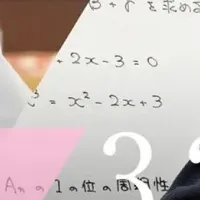








【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。