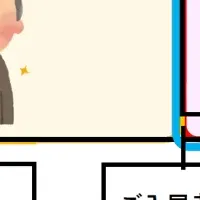
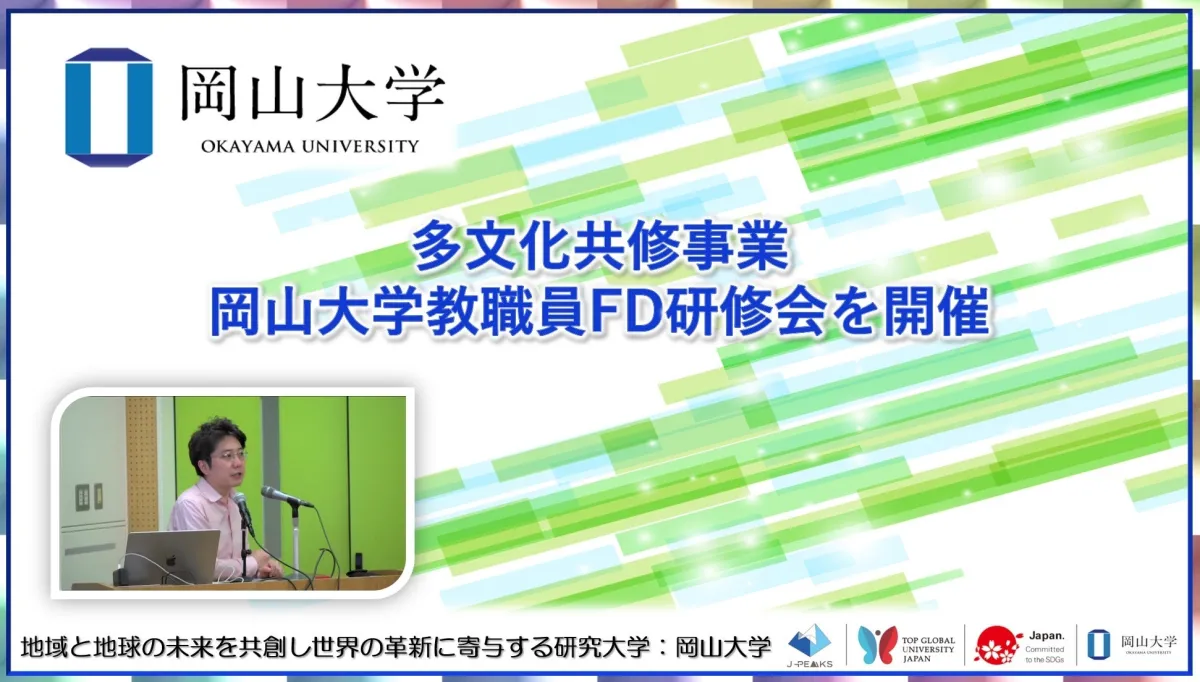
岡山大学の多文化共修事業が目指す国際化への取り組みとその成果
岡山大学の多文化共修事業が目指す国際化への取り組みとその成果
国立大学法人岡山大学(所在地:岡山市北区、学長:那須保友)は、2024年度文部科学省による「ソーシャルインパクト創出のための多文化共修キャンパス形成支援事業」に採択され、多文化共修事業を進めています。2025年9月24日には、この事業の一環として教職員向けのFD研修会「多文化共修を効果的・効率的に実践するために」が開催され、130名以上の教職員が参加しました。
研修会の内容
研修会はハイブリッド形式で行われ、鈴木孝義副学長(国際・同窓会担当)が開会の挨拶を行いました。その後、岡山大学の多文化共修事業の概要が紹介されました。その中で特に注目されたのが、横井篤文副学長(グローバル・エンゲージメント担当)と津波優UGA(グローバルエンゲージメントセンター)による講演でした。
グッドプラクティス1: アクティブな学びはAIで実現
彼らは『AI自動翻訳と意見集約アプリで実現する主体的・双方向型のグローバル学習環境』をテーマに、英語が得意でない日本人学生を対象にした取り組みを紹介。アプリを使い、リアルタイムで自動翻訳を提供する形式の授業が行われていることが説明されました。このアプローチによって、英語の授業に参加しやすくなり、語学の壁を越えて多くの学生が学ぶことができる環境が創り出されています。
グッドプラクティス2: 学習コンテンツの多言語化
続いて、香田将英特任准教授(学術研究院医歯薬学域地域医療共育推進オフィス)が『生成AIで実現する「字幕付き・多言語対応」教育動画づくり』と題し、実際にアプリを使って教育動画に字幕を付ける様子を説明しました。参加者はアプリ操作や生成AIの使い方を学び、言語の壁を感じることなく多言語教育を実践する方法を探りました。
研修の意義
参加者からは、「先進的な取り組みで役立ちそう」「発表内容が興味深く、今後の方向性に希望を感じた」といった好意的な意見がありました。この研修を通じて、多文化共修の大きな障壁である言語の問題に対し、生成AIの活用が重要な解決策となる可能性が示唆されました。
今後の展望
岡山大学は、この多文化共修事業を通じてさらに国際化を進めていく方針です。大学の取り組みが地域社会にどのような影響を与えるのか、そして未来の教育にどのように貢献するのか、引き続き注目していきたいと思います。岡山大学の特色ある取り組みが、地域中核の大学として、また世界に誇れる存在へと成長していくことが期待されます。
参考情報
詳しい取り組みや情報については、岡山大学の公式ホームページやグローバルエンゲージメントセンターのページで確認できます。
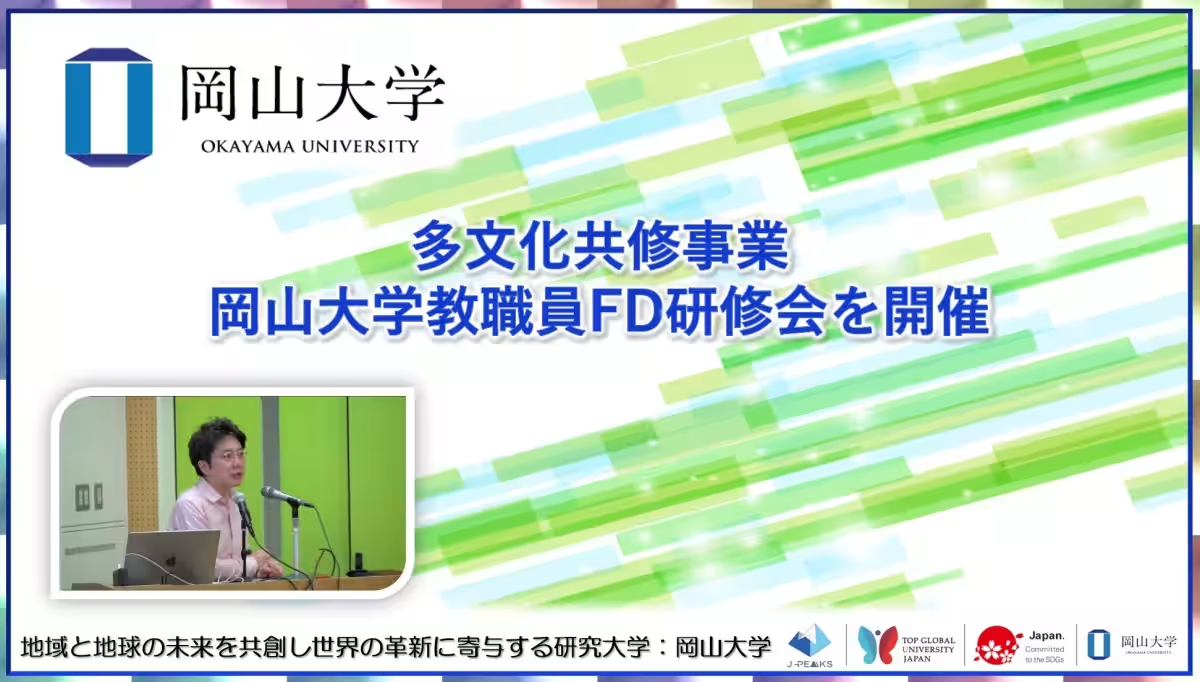








トピックス(その他)
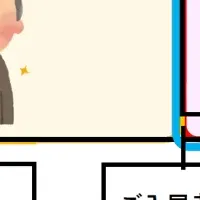
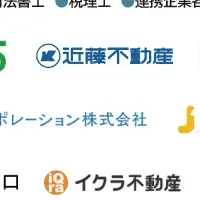
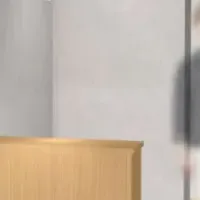






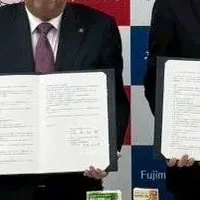
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。