

くら寿司が松江で開催する次世代へ向けたSDGs出張授業
本記事では、2025年11月13日に島根県松江市の宍道小学校で行われる、くら寿司株式会社と一般社団法人海と日本プロジェクトinしまねによる出張授業「お寿司で学ぶSDGs」について詳しく紹介します。この授業は、次世代を担う子どもたちが海洋環境や食品ロスの問題について理解を深め、持続可能な社会を実現するための取り組みです。
昨今、私たちの生活は海と密接に関連しています。しかし、漁業資源の減少や食品ロスといった問題が顕著になってきました。そこで、一般社団法人海と日本プロジェクトinしまねが立ち上げた「お寿司で学ぶSDGs」授業は、子どもたちに海の恵みやその大切さを知ってもらう機会を提供します。今回の出張授業は、島根県では初めての試みです。
この出張授業では、SDGsの目標である「つくる責任、つかう責任」や「海の豊かさを守ろう」、さらには「パートナーシップで目標を達成しよう」といったテーマに基づき、各学びを深めることを狙いとしています。
学生たちは、体験学習やワークショップを通じて、自らの行動が海や漁業資源にどのように影響を与えるのかを考える力を養います。たとえば、実際にお寿司屋さんの体験ゲームを通じて、廃棄物の削減や海の資源利用について学ぶことができます。
授業は大きく3部構成に分かれています。まず、海の資源が将来どのように変わるのかを示す映像や模型を用いた説明です。この段階で、漁業が直面する資源減少や担い手不足などの問題について、子どもたちが自分ごととして考える機会を設けます。
次に、「お寿司屋さん体験ゲーム」においては、子どもたち自身が注文に応じてお寿司を提供する役割を体験し、過剰な注文や食品ロスが生じた場合にどのような影響があるかを学びます。この実体験を通じて、資源の有効利用や食品ロスの重要性を理解することが期待されます。
最後に、グループワークが行われます。ここでは、参加児童たちが「未来の食卓をどうするか?」について意見を出し合い、持続可能な海の恵みを守るための解決策を考える時間を持ちます。このアプローチにより、子どもたちの創造性や主体性が引き出されるでしょう。
海と日本プロジェクトinしまねが2025年7月に行った隠岐諸島での体験学習「隠岐めしと歴史探険隊」では、小学生たちが地元の漁師から教わったことや、郷土料理の調理体験を通じて、地域の海にどれだけの恵みがあるかを学びました。この体験が今回の出張授業に活かされ、実際の漁業現場やその課題も取り扱います。
この授業を通じて、子どもたちが海と食の関係を理解し、自らの生活を見直すきっかけとなることを期待しています。その結果、彼らが未来の海を守るための担い手として成長することにつながれば、非常に意義深いといえるでしょう。
「お寿司で学ぶSDGs」は、単なる学びの機会ではなく、参加する子どもたちにとっての人生の大きな財産となるはずです。海と共に生き、海を未来へ引き継ぐ意志を育むこのプロジェクトに、ぜひご注目ください。皆さんも、これからの海の未来を一緒に考えてみてはいかがでしょうか?



授業の背景
昨今、私たちの生活は海と密接に関連しています。しかし、漁業資源の減少や食品ロスといった問題が顕著になってきました。そこで、一般社団法人海と日本プロジェクトinしまねが立ち上げた「お寿司で学ぶSDGs」授業は、子どもたちに海の恵みやその大切さを知ってもらう機会を提供します。今回の出張授業は、島根県では初めての試みです。
授業の目的
この出張授業では、SDGsの目標である「つくる責任、つかう責任」や「海の豊かさを守ろう」、さらには「パートナーシップで目標を達成しよう」といったテーマに基づき、各学びを深めることを狙いとしています。
学生たちは、体験学習やワークショップを通じて、自らの行動が海や漁業資源にどのように影響を与えるのかを考える力を養います。たとえば、実際にお寿司屋さんの体験ゲームを通じて、廃棄物の削減や海の資源利用について学ぶことができます。
授業内容
授業は大きく3部構成に分かれています。まず、海の資源が将来どのように変わるのかを示す映像や模型を用いた説明です。この段階で、漁業が直面する資源減少や担い手不足などの問題について、子どもたちが自分ごととして考える機会を設けます。
次に、「お寿司屋さん体験ゲーム」においては、子どもたち自身が注文に応じてお寿司を提供する役割を体験し、過剰な注文や食品ロスが生じた場合にどのような影響があるかを学びます。この実体験を通じて、資源の有効利用や食品ロスの重要性を理解することが期待されます。
最後に、グループワークが行われます。ここでは、参加児童たちが「未来の食卓をどうするか?」について意見を出し合い、持続可能な海の恵みを守るための解決策を考える時間を持ちます。このアプローチにより、子どもたちの創造性や主体性が引き出されるでしょう。
体験学習とその意義
海と日本プロジェクトinしまねが2025年7月に行った隠岐諸島での体験学習「隠岐めしと歴史探険隊」では、小学生たちが地元の漁師から教わったことや、郷土料理の調理体験を通じて、地域の海にどれだけの恵みがあるかを学びました。この体験が今回の出張授業に活かされ、実際の漁業現場やその課題も取り扱います。
取り組む価値
この授業を通じて、子どもたちが海と食の関係を理解し、自らの生活を見直すきっかけとなることを期待しています。その結果、彼らが未来の海を守るための担い手として成長することにつながれば、非常に意義深いといえるでしょう。
まとめ
「お寿司で学ぶSDGs」は、単なる学びの機会ではなく、参加する子どもたちにとっての人生の大きな財産となるはずです。海と共に生き、海を未来へ引き継ぐ意志を育むこのプロジェクトに、ぜひご注目ください。皆さんも、これからの海の未来を一緒に考えてみてはいかがでしょうか?



関連リンク
サードペディア百科事典: SDGs 海と日本プロジェクト くら寿司
トピックス(イベント)




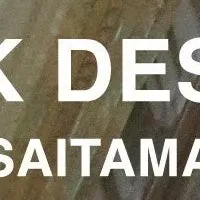


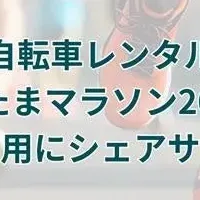
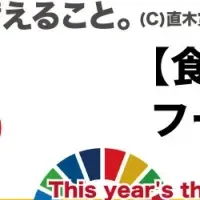

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。